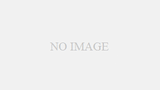こんにちは。タマダです。
ニッケルハルパに出会い、ニッケルハルパの魅力に取り憑かれ、ついにニッケルハルパを手にした方。
ようこそお待ちしていました。
「ニッケルハルパ」という沼へようこそ。
きっとこの先の人生、ニッケルハルパなしではいられなくなるでしょう。
ニッケルハルパを長く楽しんでいただければそれが一番の喜びですが、
今この時点から意識してもらえたら嬉しいことをつらつらと書き出してみます。
一言でまとめると「身体の負担を少しでも減らす」。
以下ご参考まで。
肘がテールピースより下の位置に来るように構える
テールピースよりも肘が下の位置になるようにニッケルハルパの位置を調整してください。
二の腕がテールピースに乗っかるイメージです。
結構肋骨に食い込む感覚です。
この位置だと弓を持つ腕全体が自由に動くようになります。
余分な力が入りすぎないので、身体への負荷が軽減されます。
親指を丸めて弓を持つ
弓を「持つ」。
不安定な感じがして、ぎゅっと弓を握る。
特に初めて弓を扱う人に多いですが、力が入りすぎて親指が伸び切ってしまうことがあります。
指先に力が入りすぎると腕全体にも力が入り、綺麗な音が出なかったり、すぐ疲れてしまったり、腱鞘炎になってしまうなど結構大変です。
親指と中指で輪っかを作って、そこに弓が入り込む感じです。
ニッケルハルパの弓は親指と中指で軽く支えて、人差し指で圧を調整します。
弓は弦に乗っかるので、持たなくても大丈夫です。
運指は目ではなく腕で覚える
「どこの鍵盤を抑えたらどの音が鳴るんだろう」
鍵盤の位置を見て確認しながら覚えていく。
当たり前のような気がしますが、デメリットが二つ。
・ニッケルハルパが寝る(上向きになる)ので、弓が体に刺さりやすくなる。
・覗き込むような構えになるので、背中が丸まる。
姿勢が悪いままニッケルハルパを弾いていると、体の一部に負荷がかかり悲鳴を上げます。
長く続けるためにも今この段階で鍵盤を見ずに弾く練習をしたいです。
①まず立ってニッケルハルパを構えてみてください。
②小指でA弦の「ミ」の音(7つ目の鍵盤)を押さえてください。
※ここは見て大丈夫です。
③そのままミの音を出してください。
④ミを押さえている方の腕、肘はどこにありますか。
→肘は体からどれくらい離れている「感覚」ですか。
→鏡があれば鏡を見て肘の角度を確認してください。
⑤手首はどれくらい曲がっていますか。
→普段の生活で同じくらい曲がっているのはどんな時か思い出してみてください。
⑥次に「レ」の音(5つ目の鍵盤)を薬指で押さえてください。
→④と⑤を確認してください。
⑦「レ」「ミ」と順番に音を出してください。
→「ミ」を出すときに薬指はつけたままにしてください。
⑧薬指と小指がどれくらい離れた感覚になるか確認してください。
→攣りそうになる感覚、とかパソコンのキーボードを打つ時の感覚とか
普段の生活で近いものを感じ取ってください。
⑨「ド」の音(3つ目の鍵盤)を中指で押さえてください。
⑩「シ」の音(2つ目の鍵盤)を人差し指で押さえてください。
→感覚を確認しながら上記繰り返します。
最後は端折りましたが、細かく書くとこんな感じです。
鏡を見ながらやるとさらに効果的。
ステンマとかで誰かと一緒に弾くときはその人の鍵盤を見ながら弾くと良いです。
弾かずに構えた時と音を出す時とで姿勢が変わらないように。
座奏(座って弾く)時は三つの構えをローテーション
①ストラップをつけたまま座る
メリット:立って弾く(立奏)の時とニッケルハルパの位置が変わらないので身体の感覚が崩れない。
デメリット:首に負荷がかかった状態なので、長く弾くと首が痛くなる。
②右足に乗っける
メリット:ストラップを使わないので首の負担が減る
デメリット:ニッケルハルパの位置を調整するためにクッションとか足のせ台とかが必要になることも。また慣れるまでは体が歪みやすい。
③左足に乗っける
メリット:②と同じ
デメリット:②と同じ
①〜③をローテーションして、ずっと同じ構えにならないように。
同じ構えでずっといると、身体の一部だけに負荷がかかります。
負荷をリカバーしようと身体の他の箇所が無理をして、またそこをリカバーしようと別の、、、、
という感じで全身がバキバキになります。
症状がひどいと整体や病院に行ったり、最悪の場合ニッケルハルパが弾けなくなる、なんてことも。
身体を固めない。歪ませない。
頭の隅、いやむしろど真ん中に置いていただきたい考えです。
ちなみにニッケルハルパの位置を調整する際、「足を組む」のはお勧めしません。
足を組んだ時点で身体が歪んでいるからです。
自分の身体に合うクッションとか台とかを探すのもニッケルハルパの楽しみの一つ。
作る、というのもいいですよね。
ちなみにタマダはクッションとか使わずに②と③を行ったり来たり、たまに①というのが基本です。
演奏中も身体が揺れたり大きく足を踏んだりとせわしないので、クッションとかあってもすぐ落ちる。
ストラップをつけるのは大抵演奏中に場所を移動する必要がある時です。
休憩は(できるだけ)必ず入れる
ニッケルハルパ。
弾いててとても楽しい楽器。
ましてや始めたての頃なんて、一日中弾いていても飽きがこない。
めちゃくちゃ気持ちわかります。
タマダもニッケルハルパを手にした当初はそれこそ朝から晩まで弾きっぱなしでした。
その気持ちがわかるからこそ、あえて心を鬼にして。
「必ず休みをとりましょう」
とお伝えしたいです。
30分でも1時間でも。時間じゃなくて弾いた曲数を単位にしてもいい。
とにかく適度に休んでください。
立って弾くにせよ、座って弾くにせよ、ニッケルハルパの演奏は身体への負担が想像しているよりも大きいです。
ずっと同じ姿勢で根を詰めると、ダメージが蓄積されます。
今楽しい気持ちと、これからずっと楽しい気持ち。
両方を実現するには「休む」が最適解の一つだということを忘れないでほしいです。
そしてただ休むだけでなく、ストレッチを一緒にすると良いです。
伸びをするだけでも良い。
腕(肩)を回すでも良い。
結構「パキパキッ」て音が鳴ります。場合によっては「刃牙刃牙ッッッ!!」て。
ニッケルハルパと向き合いつつ、自分の身体とも向き合ってくださいね。
弾けないところではなく、弾けてるところに目を向ける
音を出す。
音の高さを変える。
弾く弦を変える。
一曲弾いてみる。
それぞれの段階で最初からできる人、時間がかかる人などそれぞれです。
人間だもの、そんなもんです。
だからこそ、弾けないところではなく弾けるところに目を向けてほしいです。
「この曲がうまく弾けない」と捉えるよりも「この曲のここまではうまく弾けてる」。
「移弦ができない」と捉えるよりも「この弦で弾くことはできる」
気持ちが後ろ向きになると、身体も緊張します。
これまでお伝えしているように身体が固くなると負荷がかかってしまいます。
できるところに目を向けるというのは、リラックスした状態でニッケルハルパを弾けるということです。
身体と心を柔らかくして、ニッケルハルパとの長い付き合いを楽しみませんか。
最後に
ニッケルハルパは楽しい。
スウェーデンの音楽は楽しい。
これからも長くニッケルハルパを、スウェーデンの音楽を楽しんでいただければと思い、
タマダ自身も始めた頃から意識しておけばよかったという自戒も込めてお届けしました。
今度一緒にニッケルハルパを、スウェーデンの音楽を楽しみましょう!